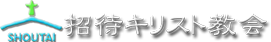2025年 年間標語 年間標語「強く、雄々しくあれ」(ヨシュア1章1~9節)
日本語の週報 ダウンロード↓↓

韓国語の週報 ダウンロード↓↓

しかし、このように便利なSNSによって、苦しむ人がいます。例えば、「ねえ、なぜ私が昨日送ったメッセージを読まないの?」といったように、SNSは関係をあまりも軽くしてしまいます。また、以前送ったメッセージの文脈を見落とし、直前のテキストだけを見て、誤解を招く場合もあるでしょう。もちろん、顔を見ながら話しても誤解することはありますが、大切な内容は互いの顔を見ながら話すべきではないかと思います。
軽率な判断による誤解を招かないためには、相手の行動をむやみに判断しないことが大切です。例えば、姑が息子の家に来た時、お嫁さんがずっと掃除ばかりしていたとしましょう。姑は自分が息子の家に来ることにお嫁さんが負担を感じて掃除ばかりしていると思うかもしれません。しかしお嫁さんは姑が来たところ、あちこちにホコリが見えて、気になったので、掃除をしていたのです。ですから、こういう時には姑が先に「お嫁さんは掃除が好きですね。」と、一言聞いてみた方いいかもしれません。相手の行動を一方的に考え、判断することがむしろ関係を複雑にする場合があります。
また、軽率に誤解しないためには、相手の表情をむやみに判断するのも避けるべきです。ある日、私が銭湯に行ったところ、向こうの人がずっとちらっと見ていて不愉快でした。しかし、独り言で「風呂椅子はどこかな」と言ったところ、その人はすぐにも風呂椅子のところを指でさしてくれました。実は親切な方だったのです。ですから、相手の表情だけでむやみに判断しないことが大切です。
また、軽率に誤解しないために、会話が苦手な人には先に聞いてみるのも良いです。私たちの周りには無口の人もたくさんいます。ですから、「何か不便なことはありませんか。」と聞いてみるのも良いでしょう。もし、相手が「いいえ、大丈夫です。」と答える時に、「あの人は自分と話したがっていない」と誤解することがあるかもしれません。しかし、自分の話をしながらもう少し声をかけてみると、その時から話してくれる人もいます。無口の人は顔見知りである傾向もあるので、むやみに判断せず、声をかけてみてはいかがですか。最初は短い返事が来るかもしれませんが、少しずつ長い会話を続けてくれるかもしれません。良い関係を作ることが人を得る道です。
趙 南洙師
日本語の週報 ダウンロード↓↓

韓国語の週報 ダウンロード↓↓

ウィスコンシン縦断研究とは、1万317名のウィスコンシン高校卒業生を対象に、一人当たりに6回ずつ「職業、日常生活、家族、現在状況、健康」などについて繰り返し調査した統計の資料に基づいて分析したものです。研究対象の女性の比率は51.6%で、平均年齢は2008年を基準に69.16歳だったそうです。
2004年に研究チームは、「普段どのようなボランティア(奉仕)をしたのか、ボランティア(奉仕)をしたのであればどのような内容だったのか。」と質問しました。そして4年後の2008年、彼らの中でどれほどの人が健康に生きているかを調査しました。結果、2004年に「近年の10年間、他人のために定期的にボランティア(奉仕)活動をしました。」と答えた人の内、1.6%の人々が2008年まで生きることができず、亡くなっていたことがわかりました。反面、「他人のためのボランティア(奉仕)活動を行ったことのない」と答えた人々の中では、ボランティア(奉仕)活動を行った人に比べて、3倍ほど高い4.3%の人々が亡くなっていました。
ここに注目すべき点があります。研究チームは「長生きできるのは、自分の健康だけにとらわれるのではなく、純粋に人々のためのボランティア(奉仕)活動を行った人々に与えられる祝福である」と結論づけました。「ボランティア(奉仕)活動を行った」と答えた人々の中で、その理由を「自己満足(健康、趣味)のために行う」と答えた人々の死亡率は、全くしない人々と比べて、ほぼその差を示さなかったそうです。そのため、研究チームは「多くの人々が自分自身のためにボランティア(奉仕)活動を行っていると答えたが、残念ながらこの類の奉仕は健康的な寿命の延長の観点から見ると自分自身にとってあまり役に立っていない。」と指摘したそうです。
ですから、「人の子も、仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分のいのちを与えるために来たのです。」(マタイ10:45)とおっしゃる主の教えこそ、イエス様を信じるすべての人々の人生にとっての原則だと思わされます。新たな2025年が始まりました。私たちの牧場こそ、人々のために仕える奉仕の場であり、同時に私たちを健康にしてくれる祝福の場であると確信します。牧場を通して、すべての信徒の健康が守られる日々となることを祈ります。
趙 南洙師