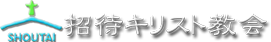2025年 年間標語 年間標語「強く、雄々しくあれ」(ヨシュア1章1~9節)
人と人との関係を築く最も基本的な要素は、互いのコミュニケーションだと思います。コミュニケーションとは、互いの思いや意見を妨げられずに話し合えることで、健全な関係を築いてくれるとても大切な要素だと言えます。そのため、「話が通じる」という感覚は、互いの信頼を築きあげ、人生をポジティブな方向へと導いてくれます。しかし、「話が通じない」と感じることは、関係を築くことが難しい証拠だと言えるでしょう。
多くの場合、コミュニケーションとは上手に話せる力、つまり会話術だと考えますが、そうではありません。コミュニケーション能力には、感情移入や相手への配慮など、多くの要素があるため、自らコミュニケーション力を訓練して育てていかなければなりません。
コミュニケーション能力を高めるためには、二つの要素が必要だと思います。一つは伝えたい言葉の内容、つまり「何を言いたいか」ということ、もう一つは相手に配慮する力、つまり「自分の言葉を聞いている相手は誰か」という認識です。
コミュニケーションに葛藤を覚えるときは、伝えたい内容と相手との関係性がうまく噛み合っていない時です。例えば、A氏はB氏との関係を考えて「この程度のことは言っても良いだろう」と思って伝えたとしても、B氏がA氏との関係をそれほど近いと思っていない場合、コミュニケーションが難しくなり、互いの心を傷つけてしまいます。ですから牧場で「どうして私にそんなことをするの?」「どうしてあんなに失礼なの?」と感じている場合、大抵はコミュニケーション力不足が原因かもしれません。ですから、牧場でのコミュニケーションにおいて葛藤を持っている方は、会話の時に内容よりも相手との関係性を考慮して話し合うと良いかもしれません。
また、コミュニケーションの葛藤を解消するためには、自分独特の頑固な表現を改善する必要があるでしょう。「私は元々こういう人間だから」と荒っぽい言葉で自分の主張を強く表明する人もいますし、自分を低くして謙遜に発言する人もいます。もちろんのことですが、高慢で強い人は、自分を低くして謙遜に話す人に比べて相手の共感を得ることが難しいでしょう。このように会話が上手く通じない人は、隣人との関係も円満でないかもしれません。「”何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分よりすぐれた者と思いなさい。(ピリピ2:3)」


我が教会では、神の導きに従う告白として、主日共同礼拝の終わりに礼拝を通して決心したことを前の席に出て告白(表現)することを勧めています。何を決意したか、どのような奉仕(献身)をしたいか、どのような祈祷課題を祈っているかを表現するように案内しています。
礼拝堂の前に出てくること自体が、決心と献身の行為だと言えます。これは決心を告白しつつ、神の御前に進み出ることだからです。このような行動は、神の御前だけでなく、会衆の前で公に告白することにつながります。イエス様を自分の人生の主として心に迎える告白を、洗礼を受ける告白を、隣人のために仕えますという決心の告白をするのです。または神の御前に進み出て、再決心を告白する場でもあります。
再献身とは、説教を聞いている時に「レーマ」、説教の中で神のみことばが自分に響き、そのみことばをもって祈ってもらいたいと願う。または教会の奉仕(事務の整理、教会学校の教師、賛美、牧者など)に対する神様からの召しを受け、その決心をもって祈ってもらいたいと願うことです。
礼拝に初めて参加された方でもこのような決心の心が生まれたならば、派遣の賛美の時間に静かに前の席まで出て下さって大丈夫です。もし一人で出て行くのが負担であれば、一緒に来た方と前の席まで出て下さっても大丈夫です。すでに信仰を持っておられる方でも、礼拝のたびに自分の信仰を再点検して、再決心することで、枯れることのない健康な信仰生活を続ける力となるでしょう。
人々の前で主を認める(告白する)ことは、神の国において自分が認められる祝福の機会を作ることです。逆に、人々の前で主を否定することは、自分も認められないという意味にもなるでしょう。(マタイ10:32~33)
今週は使徒の働き17章を黙想しながら、パウロとシラスがテサロニケで福音を伝えた際に、みことばを持って人々と議論したことに注目しました。特にパウロは、キリストが苦しみを受け、死者の中からよみがえったことを解釈し、証しつつ、イエス様こそ、キリストであることを宣べ伝えました。結果、パウロの伝道に心動かされた人々が多くおり、彼らはキリスト者となりました。すなわち、十字架の福音を先に信じたパウロの後をついていくキリストの弟子として生きる、証人となったのです。
我が教会では、聖書が語る家の教会こそ、イエス様の体としてのまことの教会の姿の回復だと信じ、信徒たちが未信者を招いて家々に集まる牧場の集いを大切にしています。しかし、食卓に招いて、少し親切なことをしたからといって、すぐに未信者の方がイエス様を信じることはないと思います。もちろん、何もしていないのに親切に接してくださり、自分のために祈ってくれる牧場のメンバーたちを見て「素晴らしい方々だ」「本当にありがたい」と思うことはあるかもしれません。家の教会は、このような隣人との健全な関係を築くことを大切にしているので、このような奉仕には感謝したいと思います。
ですが、イエス様を救い主として受け入れることは、強要、あるいは親切な奉仕を通して得られるものではありません。私たちのために十字架にかかって死なれ、そして死者の中からよみがえられたイエス様の救いのみわざを歴史的な事実として心に受け入れる時、可能になります。その時、人々はこのニュース(歴史)を自分に向けた福音として受け入れ、信じるようになるのです。
福音の受容は一般的な知識の伝達とは異なり、贖いに対する論理的な証明が必要です。それだけでなく、伝える過程においても、神の霊である聖霊様が、伝える人と聞く人に感動を与えてくださるから可能になることだと信じます。
単に聖書一箇所を引用することで福音をすべて伝えたと考えるのは、あまりにも軽率な行動のような気がします。相手が福音を納得して受け入れられるように、聖書を解き明かし、自分はどのようにして、なにゆえに救われたかをも証しする必要があるでしょう。魂の救いが単なるスローガンで終わることなく、みなさまの人生の中で実現することを願い、祈ります。
多くの場合、コミュニケーションとは上手に話せる力、つまり会話術だと考えますが、そうではありません。コミュニケーション能力には、感情移入や相手への配慮など、多くの要素があるため、自らコミュニケーション力を訓練して育てていかなければなりません。
コミュニケーション能力を高めるためには、二つの要素が必要だと思います。一つは伝えたい言葉の内容、つまり「何を言いたいか」ということ、もう一つは相手に配慮する力、つまり「自分の言葉を聞いている相手は誰か」という認識です。
コミュニケーションに葛藤を覚えるときは、伝えたい内容と相手との関係性がうまく噛み合っていない時です。例えば、A氏はB氏との関係を考えて「この程度のことは言っても良いだろう」と思って伝えたとしても、B氏がA氏との関係をそれほど近いと思っていない場合、コミュニケーションが難しくなり、互いの心を傷つけてしまいます。ですから牧場で「どうして私にそんなことをするの?」「どうしてあんなに失礼なの?」と感じている場合、大抵はコミュニケーション力不足が原因かもしれません。ですから、牧場でのコミュニケーションにおいて葛藤を持っている方は、会話の時に内容よりも相手との関係性を考慮して話し合うと良いかもしれません。
また、コミュニケーションの葛藤を解消するためには、自分独特の頑固な表現を改善する必要があるでしょう。「私は元々こういう人間だから」と荒っぽい言葉で自分の主張を強く表明する人もいますし、自分を低くして謙遜に発言する人もいます。もちろんのことですが、高慢で強い人は、自分を低くして謙遜に話す人に比べて相手の共感を得ることが難しいでしょう。このように会話が上手く通じない人は、隣人との関係も円満でないかもしれません。「”何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分よりすぐれた者と思いなさい。(ピリピ2:3)」
趙 南洙師
日本語の週報 ダウンロード↓↓

韓国語の週報 ダウンロード↓↓

我が教会では、神の導きに従う告白として、主日共同礼拝の終わりに礼拝を通して決心したことを前の席に出て告白(表現)することを勧めています。何を決意したか、どのような奉仕(献身)をしたいか、どのような祈祷課題を祈っているかを表現するように案内しています。
礼拝堂の前に出てくること自体が、決心と献身の行為だと言えます。これは決心を告白しつつ、神の御前に進み出ることだからです。このような行動は、神の御前だけでなく、会衆の前で公に告白することにつながります。イエス様を自分の人生の主として心に迎える告白を、洗礼を受ける告白を、隣人のために仕えますという決心の告白をするのです。または神の御前に進み出て、再決心を告白する場でもあります。
再献身とは、説教を聞いている時に「レーマ」、説教の中で神のみことばが自分に響き、そのみことばをもって祈ってもらいたいと願う。または教会の奉仕(事務の整理、教会学校の教師、賛美、牧者など)に対する神様からの召しを受け、その決心をもって祈ってもらいたいと願うことです。
礼拝に初めて参加された方でもこのような決心の心が生まれたならば、派遣の賛美の時間に静かに前の席まで出て下さって大丈夫です。もし一人で出て行くのが負担であれば、一緒に来た方と前の席まで出て下さっても大丈夫です。すでに信仰を持っておられる方でも、礼拝のたびに自分の信仰を再点検して、再決心することで、枯れることのない健康な信仰生活を続ける力となるでしょう。
人々の前で主を認める(告白する)ことは、神の国において自分が認められる祝福の機会を作ることです。逆に、人々の前で主を否定することは、自分も認められないという意味にもなるでしょう。(マタイ10:32~33)
趙 南洙師
今週は使徒の働き17章を黙想しながら、パウロとシラスがテサロニケで福音を伝えた際に、みことばを持って人々と議論したことに注目しました。特にパウロは、キリストが苦しみを受け、死者の中からよみがえったことを解釈し、証しつつ、イエス様こそ、キリストであることを宣べ伝えました。結果、パウロの伝道に心動かされた人々が多くおり、彼らはキリスト者となりました。すなわち、十字架の福音を先に信じたパウロの後をついていくキリストの弟子として生きる、証人となったのです。
我が教会では、聖書が語る家の教会こそ、イエス様の体としてのまことの教会の姿の回復だと信じ、信徒たちが未信者を招いて家々に集まる牧場の集いを大切にしています。しかし、食卓に招いて、少し親切なことをしたからといって、すぐに未信者の方がイエス様を信じることはないと思います。もちろん、何もしていないのに親切に接してくださり、自分のために祈ってくれる牧場のメンバーたちを見て「素晴らしい方々だ」「本当にありがたい」と思うことはあるかもしれません。家の教会は、このような隣人との健全な関係を築くことを大切にしているので、このような奉仕には感謝したいと思います。
ですが、イエス様を救い主として受け入れることは、強要、あるいは親切な奉仕を通して得られるものではありません。私たちのために十字架にかかって死なれ、そして死者の中からよみがえられたイエス様の救いのみわざを歴史的な事実として心に受け入れる時、可能になります。その時、人々はこのニュース(歴史)を自分に向けた福音として受け入れ、信じるようになるのです。
福音の受容は一般的な知識の伝達とは異なり、贖いに対する論理的な証明が必要です。それだけでなく、伝える過程においても、神の霊である聖霊様が、伝える人と聞く人に感動を与えてくださるから可能になることだと信じます。
単に聖書一箇所を引用することで福音をすべて伝えたと考えるのは、あまりにも軽率な行動のような気がします。相手が福音を納得して受け入れられるように、聖書を解き明かし、自分はどのようにして、なにゆえに救われたかをも証しする必要があるでしょう。魂の救いが単なるスローガンで終わることなく、みなさまの人生の中で実現することを願い、祈ります。
趙 南洙師